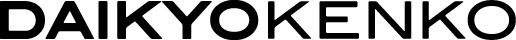“中島の家5”
狭小地で建築工事を行う場合、
どうやったって建物と隣地の塀や境界ブロックが近接してしまうわけでして、
工事中に地盤が隆起したり崩れたりしてそれらを傷めてしまう可能性があったりします。
特に地盤改良工事~基礎工事は注意が必要で、
現場では細心の注意を払いつつ作業を進めます。
また、設計段階で周辺へ影響を与えにくい工法を選ぶというのも大切です。
・・・
まず地盤改良工事。
環境パイルS工法は一般的な湿式柱状改良工法と比べると杭径が細く、
(前者はφ600mm、後者はφ120mm)地盤の隆起等も最小限で済みます。
ゆえに隣接する構造物に与える影響も最小限。

イマドキの木造住宅はベタ基礎を採用する事例が多いですが、
コレも結果的に対策となります。(布基礎と比較)
構造上、布基礎はベタ基礎と比べると土を掘る深さが深く、
また、土を掘る範囲も隣地側へ広くなりがちです。
ゆえに、
掘削工事における隣地への影響が出にくいのはベタ基礎と言えるでしょう。

配筋検査 ~ 型枠組立 ~ アンカーボルトセット ~ アンカーチェック ~
コンクリート打設(一体打設)

養生期間を経て型枠解体。
間口1.5間(2730mm) × 奥行8.5間(15470mm) の細長い基礎が完成しました。
今回は床下暖房は行わず、基礎断熱ではなく床断熱の計画ですから、
地中梁のない通常のベタ基礎としております。
また建物間口は狭いですが、普通の木造在来工法で耐震等級3をクリア。
特殊なモノを使わずに、ありふれた工法と材料で作る高性能な家を目指します。

裏の空き地をお借りして、建て方作業です。
ずいぶん作業が楽になりました。ありがとうございます。

この建物間口だと材料の取り回しにも気をつかいますね。
建物の間口(2730mm)以上の長さがある材料って色々あるから、
それらの搬出入の方法や置場をしっかりと考えておく必要があります・・・
小倉棟梁は四苦八苦です。

地味な苦労がありつつ、無事に上棟しました。
Tさん、おめでとうございます。
小倉棟梁が丁寧に進めて参ります。